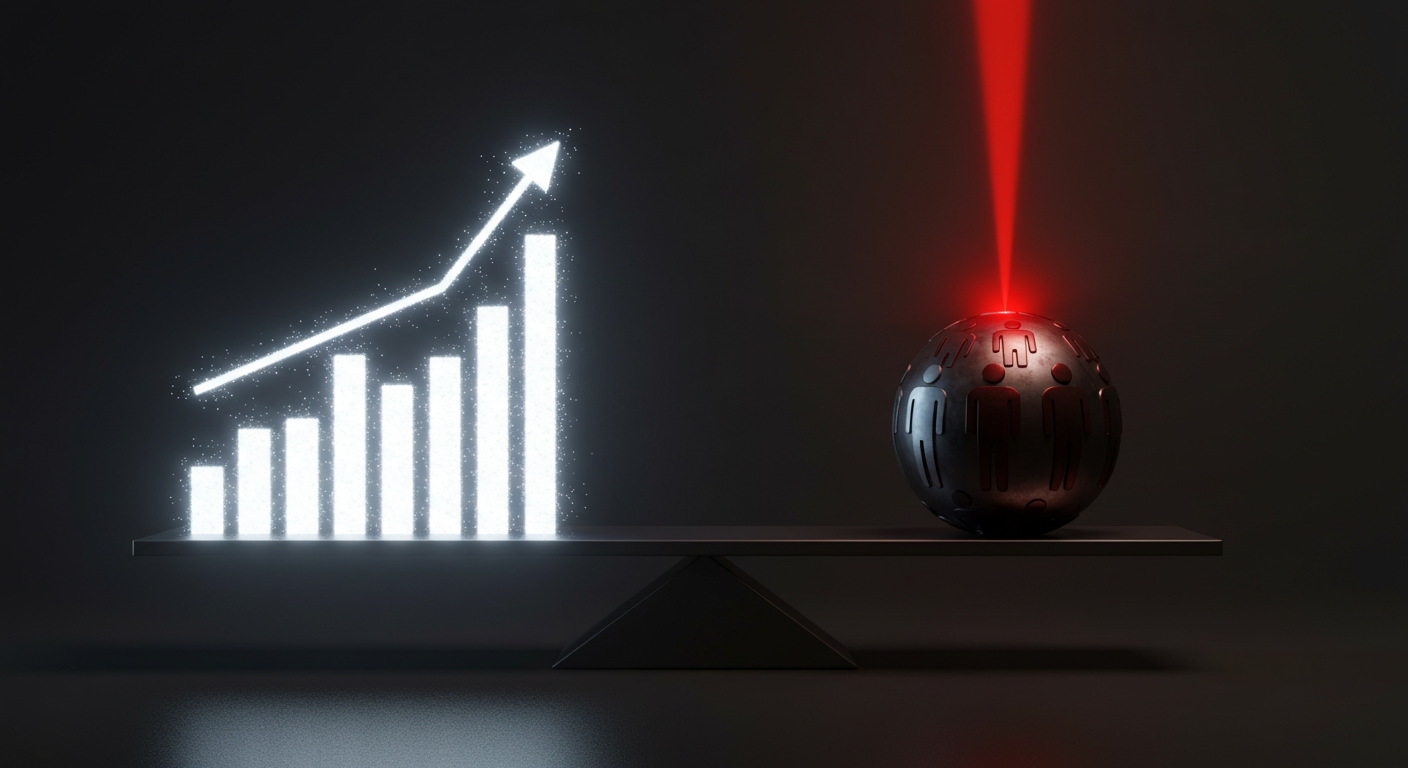
企業の民営化は、世界中の多くの国で重要な政策課題となっている。その目的は、非効率な経営を改善し、生産性を向上させることにある。しかし、その改革の裏側で、そこで働く従業員たちはどのような代償を払っているのだろうか。リストラや賃金カットといった短期的な影響だけでなく、彼らのキャリア、家族、健康、そして家計にまで、長期的な爪痕を残しているのではないか。
なぜ、企業の成長や効率化という「正しさ」が、そこで働く人々の生活を脅かすという、痛みを伴う結果を生み出してしまうのか。そして、このトレードオフに、私たちはどう向き合えばよいのだろうか。
なぜ、会社の「成長」が、従業員の「不幸」に繋がるのか?
近年、日本でも政府系金融機関やインフラ企業など、様々な分野で民営化やそれに類する改革が議論されている。例えば、JR各社の発足は国鉄民営化の象徴的な事例であり、その後の経営効率化やサービス向上は広く知られている。しかし、その一方で、大規模な人員削減が行われ、多くの従業員が職を失ったり、キャリアの転換を余儀なくされたりしたことも事実である。
こうしたマクロな変化は、私たちの現場にどのような示唆を与えるのだろうか。長年、公営のインフラ企業に勤めてきた田中さんも、自社が民営化されるというニュースを複雑な思いで受け止めていた。彼は、会社の非効率な部分を認識しており、改革の必要性も理解している。しかし、同時に、長年共に働いてきた同僚たちの顔が目に浮かぶ。「民営化によって会社が成長したとしても、そのために誰かが犠牲になるのだとしたら、それは本当に正しいことなのだろうか…」。田中は、会社の未来と、従業員の生活という二つの天秤の間で、答えの出ない問いに苛まれていた。
このような課題が多くの組織で他人事ではないのは、私たちが「企業のパフォーマンス向上」という目標を追求する際、そのプロセスで生じる「人的コスト」を軽視しがちだからだ。生産性の向上やコスト削減といった指標は、企業の貸借対照表を改善するかもしれない。しかし、その数字の裏には、職を失い、収入が減少し、将来への不安を抱える個々の従業員の人生がある。この見過ごされがちなコストを直視しない限り、真に持続可能な組織改革は実現できない。
複雑な課題を構造的に捉えるための「思考の道具」
田中さんが直面したようなジレンマを、感情論で終わらせず、構造的に分析するための思考の道具をいくつか紹介する。
民営化のトレードオフ
企業の民営化は、一般的に生産性や収益性の向上といった「便益」をもたらす一方で、従業員の雇用や賃金に負の影響を与える「コスト」を伴う。このトレードオフを定量的に評価することは、政策決定や経営判断において不可欠である。
ソーシャル・セーフティネットの役割
失業や収入減少といった民営化の負のインパクトを緩和する上で、政府による社会保障制度(ソーシャル・セーフティネット)が重要な役割を果たす。失業手当や再就職支援プログラムなどが、労働者の経済的・心理的負担をどの程度軽減できるのかを分析することは、改革の社会的コストを理解する上で重要となる。
生産性向上のメカニズム
民営化による生産性向上は、具体的にどのようなメカニズムによってもたらされるのか。それは、単なる人員削減によるものなのか、それとも新しい経営陣によるガバナンス改革や、より生産性の高い人材への入れ替え、あるいは設備投資によるものなのか。このメカニズムを解明することは、改革の効果を最大化し、副作用を最小化するためのヒントを与える。
民営化の「痛み」をデータで可視化する
この問いに対し、Olsson and Tåg (2025)が経済学のトップジャーナルである The Journal of Finance で発表した研究は、極めて貴重なデータに基づいた客観的な視点を提供している。この研究は、スウェーデンの20年間にわたる網羅的な行政記録データを用い、民営化された国有企業の従業員が、労働市場、家族、健康、家計といった多岐にわたる側面でどのような影響を受けたのかを、厳密な計量経済学的手法(差の差分法)で分析したものである。
この研究が私たちに見せてくれるのは、民営化による生産性向上という「光」の裏で、従業員が確かに経済的な「影」を背負っているという、揺るぎない事実だ。
1. 民営化は、従業員の賃金を長期にわたって押し下げる
研究が明らかにした最も重要な事実は、民営化が従業員の賃金収入に、長期的かつ深刻な負の影響を与えるということだ。民営化後、従業員の賃金収入は最初の2年間で平均5.8%、3〜4年目には9.3%、そして5〜8年目においても8.4%減少していた。
この結果が浮き彫りにするのは、民営化のコストが、一時的な解雇だけでなく、その後のキャリアパス全体に及ぶ「傷跡効果」として残る可能性である。一度職を失ったり、賃金の低い職に転職したりした従業員が、元の収入水準に回復するのは容易ではないことを、データは冷徹に示している。
2. 社会保障が、損失の半分を補填する
一方で、この研究は希望の光も示している。それは、スウェーデンの手厚い社会保障制度が、この賃金損失の約半分を補填していたという事実だ。失業手当や再就職支援プログラムといったセーフティネットが、民営化の痛みを和らげる上で、極めて重要な緩衝材として機能していたのである。
これは、私たちに重要な示唆を与える。民営化という経済合理的な改革を進める際には、同時に、その負の影響を受ける人々を支える社会的メカニズムを整備することが、政策として不可欠であるということだ。
3. 生産性向上の源泉は「CEOの交代」にある
では、民営化による生産性向上は、何によってもたらされるのだろうか。研究は、その鍵が「CEOの交代」にあることを突き止めた。民営化後にCEOが交代した企業では生産性が大幅に向上したのに対し、CEOが留任した企業では変化が見られなかった。
この発見は、生産性向上が単なる現場レベルの人員削減だけでなく、トップマネジメントの刷新によるガバナンス改革によってドライブされることを示唆している。新しいリーダーシップが、旧来の従業員との「暗黙の契約」を断ち切り、より大胆なコスト削減や組織改革を可能にすることが、生産性向上の大きな要因となっているのだ。
4. 企業の便益は、従業員のコストを上回る
そして、この研究は、民営化のコストと便益を天秤にかける上で、決定的なデータを示している。民営化による企業の生産性向上(便益)は、従業員が被る賃金損失(コスト)を、2倍から6倍も上回っていたのだ。
これは、経済全体として見れば、民営化はプラスの価値を生み出していることを意味する。そして、その生み出された余剰の一部(生産性向上の10%〜30%)が、社会保障を通じて従業員に還元されている。この事実は、民営化の利益を、企業の新しい所有者だけでなく、政府(売却収入)と従業員(補償)の間で、より公平に分配することが可能であることを示唆している。
このスウェーデンの教訓を、どう日本に活かすか?
もちろん、どのような優れた研究も、それ一つで全てを語ることはできない。Olsson and Tågの研究は、手厚い社会保障制度を持つスウェーデンという特定の国を対象としており、この結果が、制度や文化の異なる日本にそのまま当てはまるかは慎重に考える必要がある。
また、この研究は主に経済的な側面に焦点を当てており、民営化がもたらす従業員の心理的なストレスや、組織文化への影響といった、数値化しにくいコストについては、さらなる探求が必要だろう。
結局のところ、この研究は最終的な答えではなく、むしろ「企業の改革を進める際に、私たちはその人的コストをどのように測定し、誰が、どのように負担すべきか」という、より本質的な問いを私たちに投げかけているのかもしれない。
その「改革」は、誰の痛みを伴っているのか?
では、完璧な答えがないとわかった上で、私たちはこの複雑な問題とどう向き合えばよいのだろうか。
ここまでの話から見えてくるのは、企業の民営化やリストラクチャリングといった改革が、単なる経営上の意思決定ではなく、社会的な富の再分配という側面を持つ、という揺るぎない事実だ。重要なのは、改革の是非を二元論で語ることではなく、そのプロセスで生じるコストと便益を可能な限り可視化し、その分配のあり方について、ステークホルダー間で合意形成を図るという、新しい姿勢を持つことなのかもしれない。
まず、私たちの組織が計画している改革は、従業員にどのような経済的・非経済的コストを強いる可能性があるだろうか。そのコストを、私たちは客観的なデータに基づいて予測しようと試みているだろうか。
次に、そのコストを緩和するために、どのようなセーフティネットを用意できるだろうか。それは、単なる金銭的な補償だけでなく、再就職支援やスキルアップのためのトレーニングプログラムといった、未来への投資を含んでいるだろうか。
そして、改革によって生み出される便益(生産性向上や収益改善)は、株主や経営者だけでなく、従業員や社会にも還元される仕組みになっているだろうか。
もちろん、これらの論点にすぐさま答えが出るわけではない。しかし、こうした視点を持って対話を始めること自体が、これまで「仕方がない犠牲」として片付けられてきた問題に光を当て、より公正で、持続可能な改革への道筋を見出すための、重要な第一歩となるだろう。
改革の「人的コスト」を可視化するための対話リスト
この記事で得た視点を、日々の意思決定の場で実践するために、以下のような論点を定期的に自問し、チームで対話する習慣を取り入れてみてはどうだろうか。
-
コストの定量化: 計画中の組織改革(民営化、事業売却、リストラなど)が、従業員の賃金や雇用に与える短期・長期的な影響を、データに基づいて試算しているか?
-
セーフティネットの設計: 影響を受ける従業員に対し、金銭的な補償(退職金の上乗せなど)だけでなく、再就職支援、キャリアカウンセリング、リスキリング(学び直し)の機会を提供しているか?
-
便益の分配: 改革によって生まれる生産性向上や利益を、どのように株主、経営陣、そして従業員に分配するかについての明確な方針はあるか?
-
ガバナンスの視点: 改革の意思決定プロセスにおいて、従業員の代表は適切に関与しているか?改革の目的と、それに伴う人的コストについて、透明性の高いコミュニケーションが行われているか?
-
長期的視点: 短期的なコスト削減だけでなく、改革が従業員のエンゲージメントや組織全体の知識・スキルに与える長期的な影響についても考慮しているか?
#️⃣【タグ】
民営化, 労働経済学, 組織改革, 生産性, ソーシャル・セーフティネット
📖【書誌情報】
Olsson, M., & Tåg, J. (2025). What is the cost of privatization for workers?. The Journal of Finance, 80, 2107-2151.