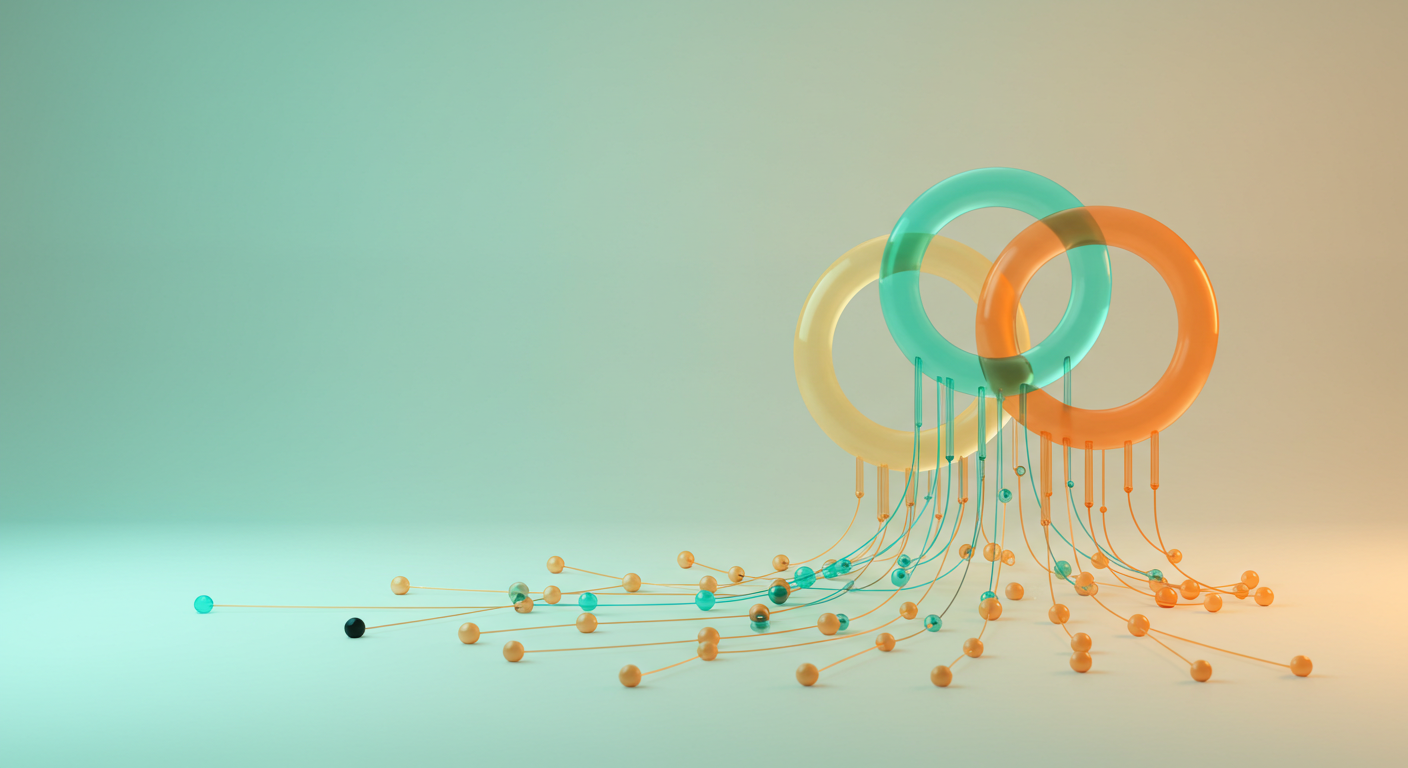
「サステナビリティ」や「SDGs」という言葉が飛び交う現代において、自社の事業にそれらをどう落とし込めばよいのか、多くの経営者や管理職が頭を悩ませている。環境活動への投資、社会貢献、従業員のウェルビーイング向上――。これらが単なるコストや美談で終わらず、企業の持続的な成長に繋がる「エンジン」となるには、一体何が必要なのだろうか。
サステナビリティの推進という正しい戦略を掲げても、なぜか現場の事業活動はなかなか変わらない。多くの企業が、同じような壁に直面しているのではないだろうか。
この根深く、複雑な課題に、私たちはどう向き合えばよいのだろうか。
なぜ、あなたの会社の「サステナビリティ活動」はコストで終わるのか?
中堅メーカーで「サステナビリティ推進室」の室長を任された佐藤部長は、焦りを感じていた。社長の特命を受け、工場の廃水削減プロジェクトや地域の清掃ボランティア活動など、次々と施策を打ち出してきた。しかし、事業部門からは「本業が忙しい」「コストがかかるだけ」といった反応しかない。活動は企業のイメージアップには多少貢献したかもしれないが、これが本当に会社の未来を創るのか、確信が持てずにいた。
佐藤部長の悩みは、決して他人事ではない。地球環境や社会課題への配慮は、もはや一部の先進企業だけの話ではなくなった。投資家、顧客、そして未来の従業員から、企業は「持続可能性」への本気度を問われている。しかし、多くの企業ではサステナビリティが「本業の横に置かれたお題目」となり、事業戦略の核に組み込まれていないのが実情である。結果として、個々の活動は生まれても、企業全体の変革には繋がらないというジレンマが、至る所で起きている。
キーコンセプト解説
この複雑な課題を感情論や根性論で終わらせず、構造的に分析するために、いくつかの「思考の道具」が役立つ。
事業の「稼ぎ方の仕組み」そのものを見直す視点
佐藤部長のケースのように、既存の事業に個別の活動を追加するだけでは、組織は本質的には変わらない。重要なのは、企業が「どのように価値を創造し、顧客に届け、対価を得るか」という事業の根幹、すなわちビジネスモデル全体を持続可能性の観点から見直すことである。このような事業の根本的な設計思想は、経営学では「ビジネスモデルイノベーション(Business Model Innovation)」と呼ばれており、持続可能な企業への変革の鍵とされている。
持続可能性を構成する「3つの資本」
「持続可能性」と聞くと、環境(Environmental)への配慮だけを思い浮かべがちだ。しかし、企業の持続的な成長には、従業員や地域社会といったステークホルダーとの良好な関係を築く「社会(Social)」資本、そしてもちろん、事業を継続するための「経済(Economic)」資本の維持・向上が不可欠である。この3つの側面を統合的に捉える考え方は「コーポレートサステナビリティ(Corporate Sustainability)」と呼ばれ、短期的な利益追求とは異なる、長期的な企業価値創造の羅針盤となる。
事業の仕組みだけでは足りない?――データが示すサステナビリティ経営の「合わせ技」
では、企業の持続可能性を高めるためには、具体的に何が重要なドライバーとなるのだろうか。この問いに対し、西バルカン諸国(コソボ、アルバニア、北マケドニア)の主に大企業に所属する168名を対象としたアンケート調査に基づく研究が、興味深い視点を提供している。この研究は、企業の持続可能性に影響を与える複数の要因を統計的に分析し、その関係性の構造を明らかにしようと試みた。
最も強力なドライバーは「従業員のサステナビリティ教育」
この研究が明らかにした最も重要な事実は、調査した5つの要因の中で、企業の持続可能性に最も強いプラスの影響を与えていたのが、「従業員への定期的なトレーニング」(パス係数 β=0.663)だったことだ。これは、後述するビジネスモデルの変革や政府の政策よりも、はるかに大きな影響力を持つという結果だった。
この結果が浮き彫りにするのは、サステナビリティ経営の成否が、経営層のトップダウンの号令だけでなく、現場の従業員一人ひとりが持続可能性の重要性を理解し、日々の業務で体現できるかに強く依存しているという可能性である。新しい事業モデルや高尚な理念も、それを理解し実践する従業員がいなければ「絵に描いた餅」で終わってしまう。この発見は、サステナビリティが「教え、学ぶ」ことができる能力やスキルであることを示唆している。
「事業モデルの変革」は土台だが、それだけでは不十分
分析の結果、事業の仕組みそのものを革新しようとする姿勢(ビジネスモデルイノベーション)も、企業の持続可能性に統計的に有意なプラスの影響を与えていることが確認された(パス係数 β=0.100)。
これは、サステナビリティを事業の根幹に据えるという戦略的な方向性を示すことが、確かに重要であることを裏付けている。しかし、その影響度は従業員トレーニングに比べると限定的だった。このことは、「稼ぎ方の仕組み」を変えるという戦略を描くだけでなく、それを実行する組織の「体質」そのものに働きかける必要性を示唆しているのかもしれない。
「権限委譲」と「政府の支援」も変革の追い風に
さらにこの研究では、「従業員へのエンパワーメントと権限委譲」(パス係数 β=0.042)と「政府の支援的な政策」(パス係数 β=0.226)も、企業の持続可能性に対して、それぞれ統計的に有意なプラスの影響を持つことが示された。
この発見は、サステナビリティへの取り組みが、従業員の自律的な行動を促す組織風土と、それを後押しする社会的なインフラの両輪によって加速することを示唆している。企業内部の努力と、外部環境からのサポートが噛み合ったとき、持続可能性への変革はより力強く進むのだろう。
意外な結果:「管理能力の高さ」が持続可能性にマイナスの影響?
興味深いことに、この調査では「管理職の能力の高さ」が、企業の持続可能性に対して、統計的に有意な「負の影響」を与えているという結果が示された(パス係数 β=-0.051)。これは、一般的に考えられている「優秀な管理職が変革を推進する」という通説とは逆の結果である。
この逆説的な結果は、私たちの思考の前提を問い直す。著者らも先行研究とは異なると指摘しているが、一つの可能性として、「従来の物差しで測られる“優秀な”管理能力」が、短期的な効率性や既存事業の最適化を過度に重視するあまり、不確実性を伴う新しい価値観(サステナビリティ)への挑戦を、無意識のうちに阻害してしまっているのかもしれない。持続可能性を推進するために求められる管理能力は、従来のものとは質的に異なるという可能性を示唆している。
明日から、あなたの「問い」をどう変えるか?
記事冒頭の「サステナビリティ活動がコストで終わってしまう」という課題に立ち返ろう。
これまでの議論を踏まえると、この問題が単なる個別の施策の良し悪しにあるのではなく、「戦略・組織・個人・外部環境」が相互に影響しあう、より構造的な要因に根差している可能性が見えてくる。つまり、この課題を乗り越えるには、これまで当然とされてきた「優れた戦略を立てれば組織は動く」「優秀な管理職がいれば大丈夫」といった思考の前提そのものを、一度疑ってみる必要がありそうだ。
この新しい視点に基づき、明日からの自身の思考やチームでの対話を、次のような問いでアップグレードしてみてはどうだろうか。
-
私たちの会社では「サステナビリティ」を、誰が、誰のために学ぶ機会を設計しているだろうか? それは、一部の担当者向けのものになっていないか? 全従業員が自分ごととして捉えるための学習機会をどう作れるだろうか?
-
私たちは「優秀なマネージャー」を、どのような基準で評価しているだろうか? その基準は、もしかすると短期的な業績や効率性に偏りすぎて、長期的な持続可能性に向けた試行錯誤を阻害してはいないだろうか?
-
新しい事業モデルを議論する際、私たちは経済的なリターンだけでなく、社会や環境への影響を最初から組み込んで考える仕組みを持っているだろうか? 従業員が自律的にサステナビリティを意識した行動を起こせるよう、どのような権限委譲が可能だろうか?
参考文献
Kajtazi, K., Rexhepi, G., Sharif, A., & Ozturk, I. (2023). Business model innovation and its impact on corporate sustainability. Journal of Business Research, 166, 114082.